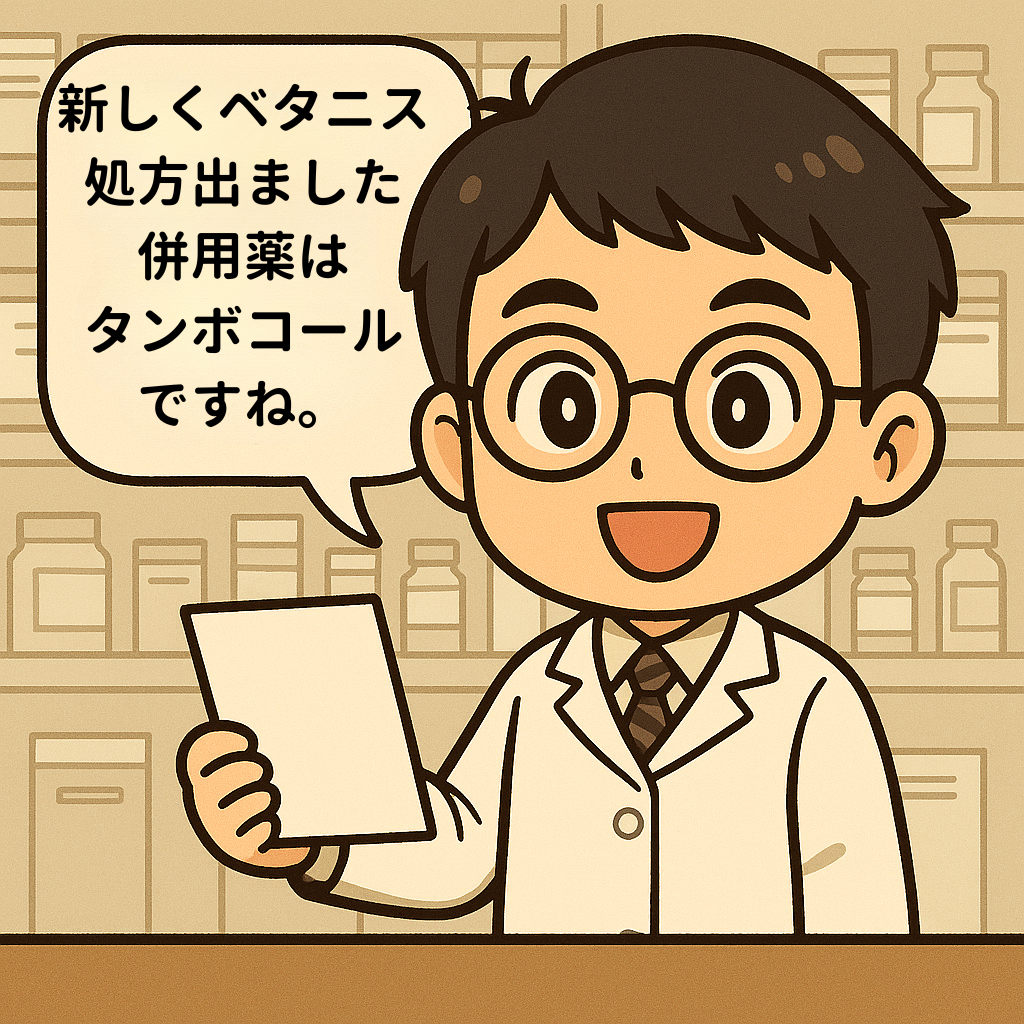



タンボコール(一般名:フレカイニド酢酸塩)は、頻脈性不整脈の治療に用いられるクラスIcの抗不整脈薬です。電気的興奮の伝導を抑制し、心筋の異常な興奮を抑える働きを持ちます。
1991年から使われる歴史あるお薬ですが、今一度使い方を見直しましょう。
タンボコールの基本情報
■ 適応症
下記の状態で他の抗不整脈薬が使用できないか、又は無効の場合
成人
○頻脈性不整脈(発作性心房細動・粗動、心室性)
小児
○頻脈性不整脈(発作性心房細動・粗動、発作性上室性、心室性)
■ 用法・用量
- 通常、成人には1日100〜200mgを2回に分けて服用(初期は100mg/dayから開始)
症状に合わせて適宜増減 - 小児6か月以上 1日50~100mg/m2(体表面積)を、1日2~3回に分けて
小児6か月未満 1日50mg/m2(体表面積)を、1日2~3回に分けて
最大用量は1日200mgまで
クレアチニンクリアランスが20mL/min以下をともなう患者では、1日量として100mg(1回50mg、1日2回)を超えないことが望ましい。
■ 禁忌
うっ血性心不全のある患者
高度の房室ブロック、高度の洞房ブロックのある患者
心筋梗塞後の無症候性心室性期外収縮あるいは非持続型心室頻拍のある患者(CAST試験※2下記に詳細あり)
妊婦又は妊娠している可能性のある女性 ※1
リトナビル、ミラベグロン、テラプレビルを投与中の患者
※1ただし2020年不整脈薬物治療ガイドラインにおける妊娠中の不整脈治療に対する評価では「おそらく安全」という区分になっています。添付文書と実態が未だ乖離した状態です。
実際の使用においては最新の情報をご確認ください。
TDM(治療薬物モニタリング)が必要な理由
タンボコールは、有効域と中毒域が非常に狭い薬剤です。
以下のような理由からTDM対象薬とされています。
- 有効血中濃度:200〜1000ng/mL
- 中毒域:>1000ng/mLでQRS延長や致死的不整脈のリスク上昇
特に、
- 腎機能低下
- 高齢者
- 相互作用を起こす併用薬(CYP2D6阻害薬など)
では血中濃度が上昇しやすいため、定期的な心電図と血中濃度測定が推奨されます。
ミラベグロン(ベタニス)との併用が禁忌な理由
■ 併用禁忌のメカニズム
ミラベグロン(ベタニス)はCYP2D6を強力に阻害する薬剤です。
タンボコールは主にCYP2D6で代謝されるため、代謝が低下し血中濃度が上昇します。
このため、以下のリスクがあります:
- QRS延長、QT延長、心停止などの重篤な不整脈
- 特に高齢者や腎機能低下例では致命的
そのため、添付文書上**ベタニスとタンボコールは「併用禁忌」**と明記されています。
■ その他の併用注意薬剤
| 薬剤名 | 注意点 |
|---|---|
| パロキセチン(SSRI) | CYP2D6阻害 →フレカイニド 血中濃度↑ |
| キニジン、シメチジン | CYP2D6強力阻害 →フレカイニド 血中濃度↑ |
| アミオダロン | フレカイニド血中濃度1.5倍 →フレカイニドの用量2/3に減量する |
| プロプラノロール | 同じCYP2D6基質のため競合する |
| フェニトイン、フェノバルビタール カルバマゼピン | 肝薬物代謝酵素の誘導→フレカイニド血中濃度↓ |
| Ca拮抗薬(ベラパミル等) | 相互に陰性変力作用と房室伝導抑制作用あり |
処方監査時には、相互作用が多い薬剤であることを前提にチェックが必要です。
不整脈治療ガイドラインにおける位置づけ
2020年改訂の**不整脈治療ガイドライン(日本循環器学会)**において、フレカイニド(タンボコール)は以下のように位置付けられています:
- 発作性心房細動の薬物治療において、心機能正常の症例に限り選択可能
- 心室頻拍では専門施設での管理下で使用されることが多い
- 構造的心疾患がある場合は原則使用しない
※2.1970年代心筋梗塞後の突然死が社会的問題となりました。心室期外収縮が突然死の指標となるこ
とから1989年心室期外収縮を抑制する治療の有効性を検証するためにCAST試験が行われました。
その結果は,I群薬のフレカイニドがかえって心筋梗塞後の突然死を増やすというものでした。
そのため心筋梗塞後は禁忌となっています。
まとめ
タンボコール(フレカイニド)は、有効性の高い抗不整脈薬でありながら、取り扱いに非常に注意が必要な薬剤です。
✔ TDM必須
✔ 相互作用多数
✔ ベタニスとは併用禁忌!
✔ 心疾患がある患者では原則禁忌!
処方時・監査時には、単なる「抗不整脈薬」ではなく、“慎重管理薬”としての意識を持つことが重要です。
免責事項
本記事は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療を推奨するものではありません。
記事中で取り上げている薬剤情報は、信頼できる資料に基づいて正確に記載していますが、
漫画内の会話やエピソードはフィクションであり、実際の医療現場の状況とは異なる場合があります。
実際の診療にあたっては、必ず医師や薬剤師等の専門家にご相談いただき、最新の添付文書等をご確認ください。
本記事の内容に基づく自己判断による治療や投薬等によって生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。


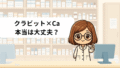
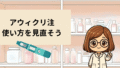
コメント