



百日咳とマクロライド:今あらためて知っておきたい基礎と実務
最近また注目されている「百日咳(ひゃくにちぜき)」ですが、咳が長引く患者さんへの服薬指導や、マクロライド系抗菌薬の選択で戸惑う場面はありませんか?
この記事では、百日咳の原因菌や症状、治療に使われるマクロライド、ワクチンの現状、そして流行動向までをまとめてご紹介します。
■ 百日咳とは?
百日咳は、Bordetella pertussis(百日咳菌)による急性呼吸器感染症で、特に乳幼児で重症化しやすいことで知られています。主な感染経路は飛沫感染と接触感染。潜伏期間は5〜10日程度、長いと3週間ほど。百日咳(ひゃくにちぜき)の名前の由来は、咳の症状が非常に長期間(おおよそ100日間)続くことにあります。
咳の特徴は「スタッカート」と呼ばれる連続的で激しい咳き込みと、ウープ音を伴う吸気。乳児では嘔吐や無呼吸発作を起こし、重症化すると肺炎・脳症など致死的な経過をとることもあります。
■ マクロライド系抗菌薬が第一選択
百日咳の治療には**マクロライド系抗菌薬(14員環)**が推奨されており、主に次の3剤が使われます:
| 薬剤名 | 特徴 |
|---|---|
| エリスロマイシン | 古典的。1日4~6回投与が必要。消化器副作用がやや多い |
| クラリスロマイシン | 1日2回。小児処方で多用される |
| アジスロマイシン(ジスロマック) | 1日1回、3日間投与で長時間効果持続。服薬コンプライアンス良好 |
マクロライドは早期(カタル期・痙咳期初期)での投与が重要で、感染性の低下や重症化防止に寄与します。一方で、発症後期では咳の改善効果は限定的となるため注意が必要です。
また、耐性菌の報告もあり、治療効果が乏しい場合には感受性試験に基づく対応が求められます。
ジスロマックについては次の記事で重点的に取り上げるので、ぜひそちらもご覧ください。
■ 予防の柱:ワクチン
日本で使用されている主なワクチン:
- DPTワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風の3種混合)
- DPT-IPV(+不活化ポリオ)
- Tdap:成人用の3種混合。特に妊婦・乳児の周囲の大人へ推奨(コクーン戦略)
初回は3回接種+追加1回が基本。
ただしワクチン効果は5~10年で減弱し、思春期以降で再感染するケースもあります。
■ 流行状況:定期的に再燃する疾患
- 百日咳は3〜5年周期で流行を繰り返す傾向があります。
- ワクチン効果の減弱、接種率の低下により成人・高齢者でも発症が増加。
- 乳児の重症例が特に問題視されており、生後3か月未満の乳児はワクチン未接種でリスクが高い。
- 日本国内でも、感染症発生動向調査によって流行の監視が続けられています。
■ 現場で意識したいポイント
- 咳が長引く患者に「百日咳」を疑う視点を持つこと
- 乳児を守るために、周囲の大人がワクチンを打つという予防戦略の啓発も
💬補足コラム:百日咳って自然に治るの?
結論から言うと、百日咳は自然に治癒することもあります。
特に、ワクチン接種歴のある健康な成人や学童では、軽症で済み、咳がしばらく続くだけで自然に回復するケースも少なくありません。
しかしながら、次のような理由から抗菌薬による治療が推奨されています。
● なぜ自然に治るのに薬が必要?
- 🧬 感染初期にマクロライド系抗菌薬を投与すると、感染力の低下や症状の短縮が期待される
- 👨👩👧👦 周囲への感染拡大を防ぐ(特に乳児や妊婦がいる家庭では重要)
- ⚠️ 重症化や合併症(肺炎、無呼吸発作など)のリスクを抑えられる
● 特に注意が必要な患者さん
| 対象 | 注意点 |
|---|---|
| 👶 生後3か月未満の乳児 | ワクチン未接種で重症化リスクが非常に高く、入院が必要なことも |
| 🤰 妊婦とその家族 | 新生児への感染を防ぐため、周囲の予防的配慮が重要 |
| 🧓 高齢者や基礎疾患のある方 | 呼吸器合併症のリスクがあるため要注意 |
自然に治るケースもありますが、百日咳は“放っておいていい咳”ではありません。
感染拡大や重症化を防ぐためにも、**早期診断・早期治療(特にマクロライド投与)**が現場では強く推奨されています。
■ まとめ
百日咳は一見「昔の病気」と思われがちですが、現在でも重症化・流行ともに注意が必要な感染症です。
マクロライド系薬の適切な使用と、ワクチンによる予防体制の理解が、薬剤師の現場対応に求められています。
患者さんへの説明や服薬指導の際に、今回の情報をぜひご活用ください。
※免責事項
本記事は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療を推奨するものではありません。
記事中で取り上げている薬剤情報は、信頼できる資料に基づいて正確に記載していますが、漫画内の会話やエピソードはフィクションであり、実際の医療現場の状況とは異なる場合があります。
実際の診療にあたっては、必ず医師や薬剤師等の専門家にご相談いただき、最新の添付文書等をご確認ください。
本記事の内容に基づく自己判断による治療や投薬等によって生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。


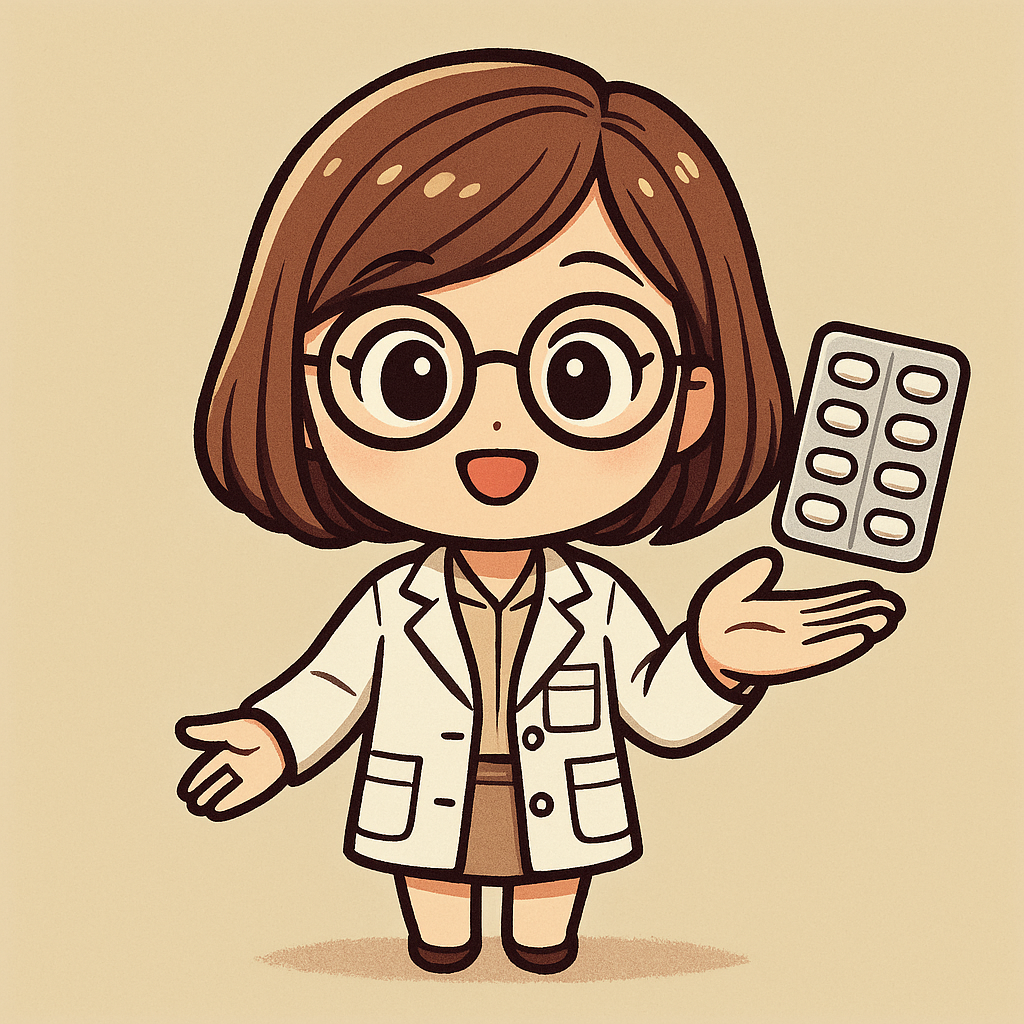
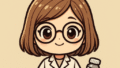
コメント